三皇五帝(さんこうごてい)とは、古代中国の神話伝説時代に登場する帝王のことを指します。
中国には、「盤古の天地開闢以来、三皇五帝が存在する」という言い伝えがあります。つまり、中国古代の人々は、国家や民族の起源を三皇五帝の説によって説明していました。
三皇五帝に関しては、さまざまな説が存在します。
例えば、三皇については、以下のような説があります。
- 『春秋運斗枢』では、伏羲(ふっき)、女媧(じょか)、神農(しんのう)の三者とする説
- 『礼号諡記』では、伏羲、祝融(しゅくゆう)、神農とする説
- 『含文嘉』や『尚書大伝』では、燧人(すいじん)、伏羲、神農とする説
また、五帝については、以下のような説があります。
- 『呂氏春秋』や『礼記』では、太皞(たいこう)伏羲、炎帝神農、黄帝(こうてい)、少皞(しょうこう)、顓頊(せんぎょく)とする説
- 『大戴礼記』、『国語』、『史記』などでは、黄帝、顓頊、帝嚳(ていこく)、堯(ぎょう)、舜(しゅん)とする説
- 孔安国『尚書序』、皇甫謐『帝王世紀』、孫氏注『世本』などでは、少皞、顓頊、帝嚳、唐堯(とうぎょう)、虞舜(ぐしゅん)とする説
- 『三統暦』では、包羲(ほうぎ)、神農、黄帝、堯、舜とする説
ここでは、広く受け入れられている説について述べます。
三皇とは、燧人氏(すいじんし)、伏羲(ふっき)、神農(しんのう)の三者を指します。
燧人氏(すいじんし)は、民に木や石を摩擦して火を起こし、食物を調理する方法を初めて教えたとされています。
伏羲(ふっき)は八卦を創り、民に漁業や牧畜を初めて教えた人物です。女媧(じょか)の兄、あるいは夫であったとも伝えられています。
神農(しんのう)は、民に薬草の効能や農耕の方法を教えたとされ、医薬と農業の発明者であり、守護神としても崇められています。
五帝とは、黄帝(こうてい)、顓頊(せんぎょく)、帝嚳(ていこく)、堯(ぎょう)、舜(しゅん)の五人を指します。時代区分としては、三皇の後、夏王朝の前に位置します。
司馬遷の『史記・五帝本紀』によると、五帝の中で最初に登場するのは黄帝です。黄帝は、文字・暦法・医薬を創始したとされています。
黄帝の死後、孫の顓頊(せんぎょく)が帝位を継ぎました。顓頊の死後、帝位を継承したのは自身の息子ではなく、姪の帝喾(ていこ)でした。帝喾の死後、その息子である尧(ぎょう)が帝位に就きました。ここまでは帝位が世襲制によって受け継がれました。
しかし、尧は自身の息子に治国の才能がないと判断し、それまでの世襲制を打破して、才能のある舜(しゅん)に帝位を譲りました。このような帝位の譲渡を「禅譲」と呼びます。
古代中国において、三皇五帝は道徳に優れた理想的な人物とされ、聖人・先覚者と見なされていました。彼らが統治した時代は仁政の時代とされ、道徳によって国を治める理想的な社会と考えられ、後の世代が努力すべき目標として語り継がれています。

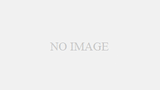
コメント