目次
1 大禹の治水と建国
2啓の王位継承と家天下の始まり
3太康の失国と後羿の政変
4少康の復国と中興
5夏桀の暴政と王朝の終焉
この記事では夏王朝の始まりから終焉までを一気に紹介します。
夏王朝は、中国史上もっとも古い王朝のひとつで、伝説と考古学が入り混じる、とてもロマンあふれる存在です。
文献によると、建国の英雄・大禹は、黄河の氾濫を見事に治めたことで、たくさんの部族から信頼を集めました。本来なら賢者・益に王位を譲る予定だったのですが、益はその王位を大禹の息子・啓に譲ったそうです。これが「家天下」、つまり王位が世襲される時代の始まりとされています。
王朝の中心地は、現在の河南省中西部から山西省南部にかけての黄河中流域。考古学的には「二里頭文化」が夏王朝と深く関係しているとされていて、河南省偃師にある二里頭遺跡からは、大きな宮殿跡や青銅器、都市の跡などが見つかっています。
そんな夏王朝は、なんと471年も続いたんです。でも、最後の王・夏桀は暴君として知られていて、贅沢三昧で民を苦しめた結果、殷の湯王によって滅ぼされてしまいました。
1.大禹(だいじゅ)の治水と建国
大禹(本名:姒文命)は、中国古代の伝説に登場する聖王であり、夏王朝の創始者として知られています。彼のもっとも有名な功績は、黄河の洪水を治めたことです。
父・鲧(こん)は洪水を「せき止める」方法で対処しようとしましたが、うまくいきませんでした。そこで大禹は「水を導く」方法を選び、川の流れを整えて海へと導くことで、洪水を抑えることに成功しました。この治水作業にはなんと13年もかかり、その間に「三度家の前を通っても中に入らなかった」というほど、仕事に打ち込んでいたそうです。
この偉業によって人々の尊敬を一身に集めた大禹に、舜帝は王位を譲りました。こうして大禹は夏王朝を築き、中国史上初の世襲制王朝が誕生します。その後、息子の啓が王位を継ぎ、「家天下」の時代が始まったのです。
2.啓(けい)の王位継承と家天下の始まり
実は、大禹は最初から息子の啓に王位を譲るつもりではありませんでした。彼は、尭や舜の時代から続く「禅譲制(ぜんじょうせい)」を守ろうと考え、賢者・伯益(はくえき)を後継者に選びました。伯益は治水にも功績があり、徳も才も備えた理想的な人物だったのです。
しかし、啓はそれに納得しませんでした。大禹の死後、啓は夏后氏という強力な部族の力と父の名声を背景に、伯益に対して王位を奪う戦いを仕掛けます。この争いは激しく、啓は一時伯益に反撃されて拘束されるほどでしたが、最終的には伯益を打ち破り、王位を手に入れました。
その後、啓は自らの支配を固めるために「甘(かん)の戦い」を起こし、反抗的だった有扈氏(ゆうこし)という部族を討伐しました。この勝利によって「天下咸朝(てんかみなちょうす)」、つまり諸侯がこぞって朝貢する体制が整い、夏王朝が本格的に始まったのです。
この王位継承の波乱は、「禅譲制」の終わりを意味し、中国史における長い「世襲制」の幕開けとなりました。啓こそが、中国史上初の本格的な世襲君主と言えるでしょう。
3.太康(たいこう)の失国と後羿の政変
太康は啓の息子で、父の後を継いで夏王朝の王となりました。しかし、彼は政治にはまったく関心を持たず、狩りと贅沢な暮らしに夢中になってしまいます。大勢の家臣を引き連れて狩りに出かけることが多く、ある時には洛水の南岸で「十旬(約100日)も帰らなかった」と言われています。
その間、朝廷は放置され、民は苦しみ、諸侯たちも次第に離反していきました。そんな中、東夷の首領・後羿(こうげい)がチャンスを見逃さず、政変を起こして夏王朝の都・斟鄩(しんじん)を占領。太康の帰路を断ち、王としての立場を奪ってしまいました。
太康が洛水に戻った時には、すでに反撃する力もなく、流浪の身となってしまいます。後羿はすぐに自ら王位につくことはせず、太康の弟・仲康(ちゅうこう)を傀儡として立て、自分が実権を握る形で支配を続けました。
この政変によって、夏王朝の正統な統治は約40年間も途絶えることになります。ですが、太康の孫・少康(しょうこう)が後に復国運動を起こし、夏王朝の支配を取り戻すことに成功します。
4.少康(しょうこう)の復国と中興
太康が国を失った後、夏王朝の支配は東夷の首領・後羿(こうげい)によって奪われました。さらに後羿が亡くなると、彼の臣下・寒浞(かんさく)が権力を乗っ取り、少康の父・姒相(しそう)を殺害。夏王室はほぼ壊滅状態となってしまいます。
少康は姒相の遺腹子として生まれ、母・后缗(こうびん)に連れられて外祖父の有仍氏(ゆうじょうし)の部族のもとで育てられました。幼い頃から夏王朝の復興を志し、成人後には有虞氏(ゆうぐし)に迎えられ、小さな領地「纶邑(りんゆう)」を与えられます。さらに、有虞氏の二人の娘を妻に迎え、支援を受けながら力を蓄えていきました。
纶邑では、農業を発展させながら、流亡していた夏族の人々を集め、少しずつ勢力を拡大していきます。善政を施すことで民の心をつかみ、諸侯たちの支持も得ることができました。
少康は、間者(スパイ)を送り込んだり、敵を内側から切り崩したり、旧勢力と連携したりと、さまざまな戦略を駆使して寒浞とその息子たちを打ち破り、ついに都・斟鄩(しんじん)を奪還。夏王朝の統治を見事に復活させました。
その後は、宗法制度の再建、祭祀の復興、軍備の強化などを進め、政治・軍事・文化の三つの面で本格的な「中興(ちゅうこう)」を成し遂げます。
この「少康中興」は、中国史上初の王朝復興の成功例とされており、夏王朝の命運をつなぎ、後世に「中興」という概念を残すきっかけとなりました。
5.夏桀(かけつ)の暴政と王朝の終焉
夏王朝は、大禹によって建国されてから約471年間続き、十四代十七人の王が治めました。そして最後の王となったのが、履癸(りき)とも呼ばれる夏桀です。彼は第十七代君主であり、第十四代の王でもあります。
夏桀は歴史上でも有名な暴君のひとり。贅沢な暮らしに溺れ、妺喜(ばっき)という美女を寵愛し、酒と快楽にふける日々を送りました。民の苦しみには目もくれず、豪華な宮殿「琼室瑶台(けいしつようたい)」を建て、「酒池肉林(しゅちにくりん)」という贅沢の極みのような宴を開いて楽しんでいたと伝えられています。
その暴政により民の不満は高まり、ついに商族の首領・湯王(とうおう)が立ち上がります。彼は「徳なき者に天下を治める資格はない」として、夏桀を討伐。これが「湯伐桀(とうばつけつ)」と呼ばれる政権交代であり、夏王朝はここに幕を閉じました。
大禹から始まり、啓、太康、少康、そして桀へと続いた夏王朝の歴史は、まるで曲がりくねった山道のよう。英雄もいれば、暴君もいました。人々の願いと天命が交差する中、王朝はやがてその役目を終え、湯王の手によって新たな時代が幕を開けました。歴史は繰り返しますが、そこに刻まれた教訓は、今も風のように語り継がれています。
次は商王朝について書いてみたいと思います
参考文献
・吕思勉著『中国通史』
・司馬遷著『史記』

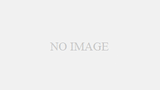
コメント